

開発現場の課題解決に役立つ!実装からチーム運営まで現場の知恵まとめ
最終更新日:2025年12月09日

開発現場は実に千態万様で、開発手法やプロジェクトの推進方法など、多様な成功例・失敗談があるかと思います。初めてプロジェクト推進を任される、新しい開発手法に挑戦するといった場合、「開発するうえで気をつけるべき点や、プロジェクト推進中に直面した課題などを知りたい」と思われるのではないでしょうか。 そこで、本記事では現場のエンジニアが実際に取り組んだ施策や、開発を成功に導くためのノウハウをまとめてお届けします。今後の開発現場に活かせる内容となっていますので、興味がある方はぜひ一読してみてはいかがでしょうか? ※尚、こちらはPR記事ではございません。編集部が独自にテーマを選び、サイト担当者に許可を頂いて作成している記事です。また、記載中の内容は、執筆時の情報になります。
330,000件の中から 希望に合う案件を探せる
- 20社以上のエージェント案件をまとめて検索
- 新着案件をメールで受け取れる
簡単60秒!あなたにピッタリの案件が届く
無料会員登録vonxai blog(vonxai合同会社)
現代のソフトウェア開発現場は、技術的な複雑さ、組織運営の難しさ、そしてセキュリティ脅威の増大という、多岐にわたる課題に直面しています。こうした複雑な問題に対し、従来の経験則や慣習だけでなく、学術研究に基づいた確かなデータと実証的な知見を活用することが、現場の課題解決に不可欠です。
vonxai合同会社は、AI時代における情報技術の本質と向き合うことをミッションとし、AI拡張型エンジニアリングやクラウドネイティブアーキテクチャを基盤に、開発生産性向上やサプライチェーン最適化を支援する技術企業です。同社はBacklogメトリクスによる生産性支援やキャラクターAI開発、環境に配慮したITインフラ構築など、多様なサービスを展開することで、現場の課題解決を支援しています。
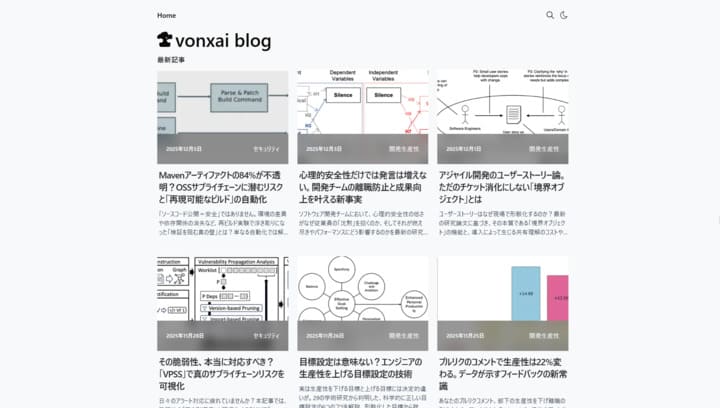
同社が運営する『vonxai blog』は、まさにこのデータに基づく課題解決を体現する情報源です。実務で培われた知見と、研究論文や大規模データ分析による科学的な視点を融合させ、エンジニアやマネージャーの意思決定に確かな根拠を提供することを主眼としています。ブログは「開発生産性」「セキュリティ」の2つの領域で構成されています。
開発生産性の分野では、開発者のゾーンに入る技術、目標設定の科学的なコツ、プルリクエストコメントが生産性に与える具体的な影響など、チームと個人のパフォーマンスを向上させるための実証的な知見を提供。また、セキュリティの分野では、ソースコード公開=安全ではないという警鐘、OSSサプライチェーンのリスク、AIコード生成に伴うセキュリティ脅威など、差し迫った課題への対策を解説しています。
同ブログは、実装からチーム運営、セキュリティ対応に至るまで、経験則だけでは立ち行かなくなった現代の開発現場において、データに基づいた確かな意思決定を可能にする知のよりどころとなるでしょう。
■vonxai blog
https://blog.vonxai.co.jp/
コラム(フレシット株式会社)
現代のシステム開発では、技術的な実装からチーム運営まで多様な課題に直面する中で、実践的な解決策を求める声が高まっています。実際のプロジェクト経験に基づいた具体的なノウハウを学べる場は、エンジニア個人の成長にとって非常に大きな意味を持ちます。
フレシット株式会社は、システムの受託開発から運用保守まで幅広いサービスを展開するIT企業です。同社は特にフルスクラッチ開発によるシステム開発コンサルティングを強みとし、プロジェクトの立ち上げから完了まで一貫した支援を提供。基幹システム連携や急成長するSaaS市場での収益化を踏まえたサービス開発支援など、多角的なアプローチで企業のDX推進を後押ししています。

同社が運営するコラムでは、個人の成長と実務能力向上に直結する実践的なノウハウを発信しています。フルスクラッチ開発の価値を論じた記事では、ノーコードやパッケージソフトが普及する現代において、フルスクラッチ開発が持つ独自性と価値について詳しく解説。自由度の高い開発による競争優位性の確保や、既製品では対応できない特定ニーズへの対応方法など、適切な開発手法選択の判断基準が学べます。
システム品質に関する記事では、特別なツールや深い専門知識がなくても実践できる3つの基本チェックポイントを紹介。古い端末・ブラウザでの表示確認、エラーハンドリングの実態確認、セッション管理の基本動作確認といった、見落とされがちな実害に直結するリスクを含む観点を具体的に解説しており、日々の品質向上に直接活用できます。
そのほかにも、セカンドオピニオンの活用や契約形態の違いなど実務課題への対処法から、決済システム実装や脱Excel化といった具体的な技術領域まで幅広くカバーしています。
個人のスキルアップから独立時の知識武装まで、幅広い場面で活用できる実践的な情報が豊富に揃った同コラムは、キャリア発展を支える強力な学習リソースといえるでしょう。
■コラム
https://freshet.co.jp/column/
「概念モデル」の導入と効果(株式会社 asken)

株式会社askenは、AI食事管理アプリ「あすけん」の開発・運営を手掛ける企業です。同社ではPHPからKotlinへシステムの移行を進めており、協力者である業務委託の方にアプリの全体像を迅速に知ってもらうため「概念モデル」を導入しています。
概念モデルとは何か、また導入後にどのような効果が得られたのか。
その答えを、『あすけん テックブログ』に掲載されている《「概念モデル」の導入と効果》という記事から紐解いていきます。
記事によると、同社が作成した概念モデルは「サービスを構成する要素に名前をつけ、それらの関係性を線で結んだシンプルな図」だそうです。さらに、各概念に対して仕様やバリエーション、説明などを追記して使用していると書かれてます。
図の作成にはMiroを採用。同時編集が可能で、かつさまざまな表現にも対応できることが、採用の決め手になったそうです。
また、概念モデルは定期的に設計・見直しを行い、関係者に共有しているとのこと。必要に応じて関係者とのディスカッションも実施し、再度認識を合わせているといいます。
記事には、概念モデルの導入後、以下のような効果があったと書かれています。
・関係者が同じ用語で話せるようになった
ユビキタス言語の確率により、メンバー内での認識のずれが起こりにくくなったそうです。
・オンボーディングの資料として活用
サービスを構成する概念が一覧化されているだけでなく、関係性も可視化されているため、新メンバーが全体像を理解しやすくなったといいます。
記事本文には「概念」の説明をはじめ、作成プロセスや見直しのタイミング、効果などの詳細について、図を用いて分かりやすく書かれています。概念モデルが気になる方、作ってみようかなとお考えの方は、ぜひ記事本文で確認してみてくださいね。
■「概念モデル」の導入と効果
https://tech.asken.inc/entry/20241219
LIFULL HOME’S の UI 構築を手助けするコンポーネントカタログを作った話(株式会社LIFULL)

株式会社LIFULLは、不動産・住宅情報サービス[LIFULL HOME’S]を主力に、介護施設検索や不動産投資など、暮らしに関わるさまざまな情報サービスを展開する企業です。1997年の設立以来、「利他主義」を社是に掲げ、「あらゆるLIFEを、FULLに。」をコーポレートメッセージに、人々の暮らしをより豊かにする取り組みを続けています。
そんな同社が運営する『LIFULL Creators Blog』から紹介するのは、こちらの《LIFULL HOME’S の UI 構築を手助けするコンポーネントカタログを作った話》という記事です。
この記事では、UIの開発効率と品質向上に向けた取り組みについて紹介されており、開発現場での実務に役立つヒントが得られることでしょう。
というのも、Webサービスの開発現場では、UIコンポーネントの再利用性と品質の一貫性が課題の一つとして挙げられることが多いようです。とりわけマイクロサービスアーキテクチャを採用する環境では、同じようなUIの実装を各サービスで個別に行うケースが増え、開発効率や品質の維持に課題を感じるチームも少なくないといわれています。
記事では、筆者がこうした課題を解決するために作ったコンポーネントカタログについて解説。「誰もが汎用的に使える実装リファレンス集」を目指し、さまざまな工夫を凝らしたといいます。
筆者は、コンポーネントカタログで実現させたいこととして、以下の3つを挙げました。
・技術スタックに依存せずコピー&ペーストが可能
・品質の高いマークアップとアクセシビリティ
・自由なカスタマイズ
特に注目したいのは、「技術スタックに依存せずコピー&ペーストできる」という点です。筆者は、npmパッケージとして配布する方法ではなく、あえてコピー&ペースト方式を採用。その理由として、カスタマイズの自由度が高く、各サービスへの最適化がしやすいことを挙げています。
続いて、コードの出力形式の柔軟な設定や、アクセシビリティに関する実践的な配慮まで、細部にわたる工夫が紹介されています。詳しい実装方法については、ぜひ記事本文をご覧ください。
開発効率と品質の両立という普遍的な課題に対して、一つの解決策を示した意欲的な取り組みといえるでしょう。
■ LIFULL HOME’S の UI 構築を手助けするコンポーネントカタログを作った話
https://www.lifull.blog/entry/2024/09/25/090000
システム開発グループのガイドラインの見直しと活用のポイント(株式会社アトラス)
株式会社アトラスは、「研究者が研究に専念できる世界へ」というビジョンを掲げ、学術コミュニケーション分野に特化したサービスを開発・提供しています。具体的には、学術大会支援や会員管理支援、ジャーナル支援など、研究者の事務的負担を軽減するITサービスを展開。年間500を超える学協会にサービスを提供し、研究者が研究活動により多くの時間を費やせる環境づくりに貢献しています。

そんな同社が運営する『Atlas Developers Blog』から、システム開発現場で役立つ記事を見つけました。
こちらの記事《システム開発グループのガイドラインの見直しと活用のポイント》では、開発チームにとって重要なコーディングガイドラインの活用方法が綴られています。
開発現場において、ガイドラインの整備は品質管理の基本となります。チーム規模が大きくなるほど、コードの書き方や命名規則などにばらつきが生じやすく、それは保守性の低下やバグの温床となりかねません。そのため、チーム共通の指針となるガイドラインの存在は、開発効率と品質の両面で重要な役割を果たします。
記事では、筆者がそうしたガイドラインの本質的な意義から実践的な活用方法までを詳しく説明。コードの書き方を統一することで、チーム全体の保守性向上やサービス品質の向上につながると述べています。
また、重要なのはガイドラインを「作るだけでなく使い続けること」なのだそう。そこで、無理のないルール設定や定期的な見直し、チェックリストの作成、構文チェックツール[ESLint]の導入など、具体的な工夫を紹介しています。
続いて、HTMLやCSS、TypeScript、アクセシビリティなど各種ガイドラインの見直し事例も詳しく解説。ガイドラインの作成から運用まで、実践的なノウハウが詰まっています。
この記事は、開発チームでガイドラインを整備したい方、既存のガイドラインを見直したい方にとって、貴重な参考資料となるでしょう。ぜひ記事全文に目を通し、開発プロセスの改善にお役立てくださいね。
■システム開発グループのガイドラインの見直しと活用のポイント
https://devlog.atlas.jp/2024/04/25/5415
リファクタリングとは?開発で必要な理由と注意点(ProFuture株式会社)
ProFuture株式会社は、人事向けポータルサイト「HRプロ」を運営する企業です。
2007年に人事採用担当者向けのポータルサイトからスタートした同社は、「HRサミット」などの人事向けフォーラムも運営しており、その領域を拡大。
現在は、経営層向けの情報サイトやフォーラムも運営するなど、新しい領域への挑戦を続けています。
さらに、同社では『マーケトランク』というWebマーケティングに特化したメディアも運営しており、マーケティングやWeb制作の基礎知識やトレンドニュースなどを発信しています。
今回は、その中から《リファクタリングとは?開発で必要な理由と注意点》という記事をご紹介しましょう。

こちらは、ソフトウェア開発において欠かせないプロセスである「リファクタリング」について解説した記事です。
リファクタリングとは、「プログラムの挙動を変えずにコードを整理・改善すること」。コードの読みやすさや品質の向上を目的とするリファクタリングは、スピードを重視するアジャイル開発においても重要な手法の一つとされています。
記事によると、リファクタリングはコードの複雑化やバグの発生を防ぐために有効な手法なのだそう。コードを整理することで、解読しやすくなったり、共有や引き継ぎが簡単になったりと多くのメリットがあるようです。
しかし、一方で作業負荷が増えるなどのデメリットもあるとのこと。記事では、リファクタリングのメリット・デメリットについてそれぞれ丁寧に解説されています。
記事の後半では、リファクタリングを実施するタイミングや主な方法の例について紹介。さらに、実施時の注意点についても言及しており、「ポイントをおさえて優先度を決める」「作業を細かく分ける」の2つを紹介しています。
時間やコストを無駄にしないためにも、注意点をよく理解しリファクタリングを行うようにしましょう。
コードの品質は、時間やコストに関わるだけでなく、ひいてはビジネスにも大きな影響を与えます。記事を参考にリファクタリングを実施して、コードの改善や品質の向上に努めてみてはいかがでしょうか?
■リファクタリングとは?開発で必要な理由と注意点
https://www.profuture.co.jp/mk/column/what-is-refactoring
優れたアジャイルチームは壁を越えてコラボレーションする!(株式会社ラジコード)

アジャイル開発は、システムやソフトウェア開発におけるプロジェクト開発手法の一つです。素早い開発を行える手法として認知度が高いので、経験したことがある方も多いでしょう。
そこで、今回は株式会社ラジコードが運営するブログの《優れたアジャイルチームは壁を越えてコラボレーションする!》という記事に注目してみました。こちらの記事では、アジャイル開発の特徴やメリットなどを紹介しています。
記事によると、アジャイル型の開発では、機能ごとに工程を細かく区切り、それぞれの工程を繰り返して完了させる特徴があるのだそう。一方で、ウォーターフォール型の開発は、プロジェクトのスタート時に決めた要件に基づいて段階的にプロダクトを開発していくという違いがあるそうです。
また、優秀なアジャイルチームを作るためには、主語の認識合わせも重要とのこと。「私」ではなく「私たち」で合わせることで、結束したチームを形成し、開発を進められるそうです。また、アジャイルチームの成長には個人の成長よりも時間がかかるため「タックマンモデル」を参考にした成長モデルを理解することが重要だと語っています。タックマンモデルについての記事もあるので、気になる方はぜひサイトを訪問してみてください。

アジャイル開発では、開発、販売、運用の3つのフェーズに専門家が協力し、迅速にプロジェクトを推進します。チームは常に状況を把握し、顧客ニーズに合わせて製品を改善して成長させることで、ユーザーに価値の高いプロダクトを提供できると記事に記述されています。
同社では、定額制受託開発でアジャイル開発を採用していることもあり、記事は非常に説得力のある内容です。
ほかにも、IT業界・新規事業開発関連について書かれた記事がたくさんありますので、興味がある方はぜひ一度サイトをご覧ください。
■優れたアジャイルチームは壁を越えてコラボレーションする!
https://blog.radicode.co.jp/development/2834
コーポレートサイト
https://radicode.co.jp/
システム開発のしくじり経験から学ぶ、ユーザ側と開発側の埋められない溝とは何か?(株式会社すまいる顔)

皆さんはこれまでの開発経験で、開発側とユーザー側で見ている視点の違いを意識したことはありますか?
開発過程では、「ユーザーの了解をとり仕様を確定させたい開発側」と「巻き込まれたくないユーザー側」の構図が生まれやすいのだそうです。
そこで今回、株式会社すまいる顔が運営するブログの『システム開発のしくじり経験から学ぶ、ユーザ側と開発側の埋められない溝とは何か?』という記事に注目。これから経験するかも…という方も参考になる内容です。
こちらの記事では、株式会社すまいる顔がシステム開発に携わったユーザー企業の方へ、インタビューをした内容を紹介しています。
インタビューを受けた金融系企業に勤務しているIさんは、入社3年目の若手社員の時に、社内システムの新規開発プロジェクトのリーダーを経験したのだとか。Iさんはこの経験の中で、「目の前のことでいっぱいな若手社員より、業務経験がある人や会社全体の課題と捉えて動ける人が主導となったほうがいい」と感じたそうです。コストや課題解決の視点からも、会社全体の課題と捉えてやらなければ迷走すると語っています。
一方で筆者は、開発担当者としての立場とユーザ側の立場両方を経験。仕様を確定したい開発サイドと巻き込まれたくないユーザーサイドの構図はどんな開発プロジェクトにおいても見られると語っています。
それも踏まえ、Iさんは筆者の「なぜユーザー側と開発側に溝が生じてしまうのでしょうか?」という質問に下記のように回答しています。
・ユーザ側はシステム開発に協力することが仕事の一部として認識していない
・関わっても評価される仕組みがない
上記の課題は、ユーザ側にとって協力するメリットが何かを明確にすることで、解決できるかもしれないと語っています。
そのほか、「システム外注の落とし穴」や「業務をシステムに合わせる」ことについても記事内で言及。業務管理をサポートするサービスを提供している同社ならではの目線から、パッケージシステムの導入についても触れています。
開発側とユーザー側に起こる評価の違いに関心がある、違う視点から開発を考えてみたい…など、興味がある方はぜひご一読ください。
■システム開発のしくじり経験から学ぶ、ユーザ側と開発側の埋められない溝とは何か?
https://smilekao.com/news/5160
トップページ
https://smilekao.com/
簡単60秒!あなたにピッタリの案件が届く
無料会員登録 次の案件探しの
情報収集ができる!
掲載数は330,000件!
あなたにピッタリの
フリーランス案件が見つかる
133万件以上のフリーランス案件から一括検索
339,879件※の案件を保有しており、エンジニアやクリエイター向けを中心にたくさんの案件を一括検索可能です。
※ 2月12日(Thu)更新
2あなたの経験やスキルに適した案件をメールでお知らせ
マイページに入力して頂いた経験や希望条件に合わせて、ご希望にマッチした案件をメールでお送りするので効率的な案件探しが可能です。


フリーランスの案件を検索する
- 関東
- 北海道・東北
- 甲信越・北陸
- 東海
- 関西
- 中国
- 四国
- 九州・沖縄
人気の記事
あわせて読みたい関連記事

集客アップにつながる!参考にしたい「SEO施策」のブログまとめ
SEOは[Search Engine Optimization(直訳すると「検索エンジン最適化」)]の略称です。具体的には、検索結果の上位表...
最終更新日:2026年01月20日

LP制作の悩みを即解消!すぐに試したくなる集客方法や改善方法を紹介
「ユーザーの目を惹くようなページを作りたい」「集客をもっと上げたい」という思いから、クオリティの高いLP(ランディングページ)の制作に興味を...
最終更新日:2025年06月02日

フロントエンドエンジニアに役に立つ資格とは?資格とその勉強方法をチェックしよう!
Webサイトやアプリケーションにおいて、ユーザーの目に触れる部分がフロントエンドです。フロントエンドは、ユーザー側の目線を最も重視する部分。...
最終更新日:2025年05月23日







